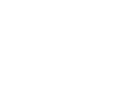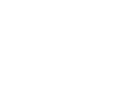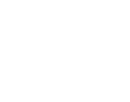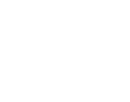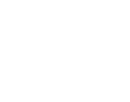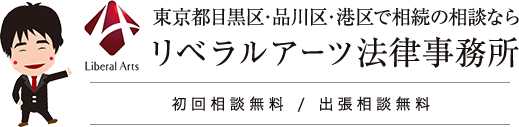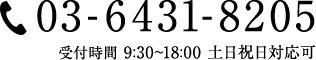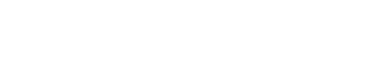遺留分とは
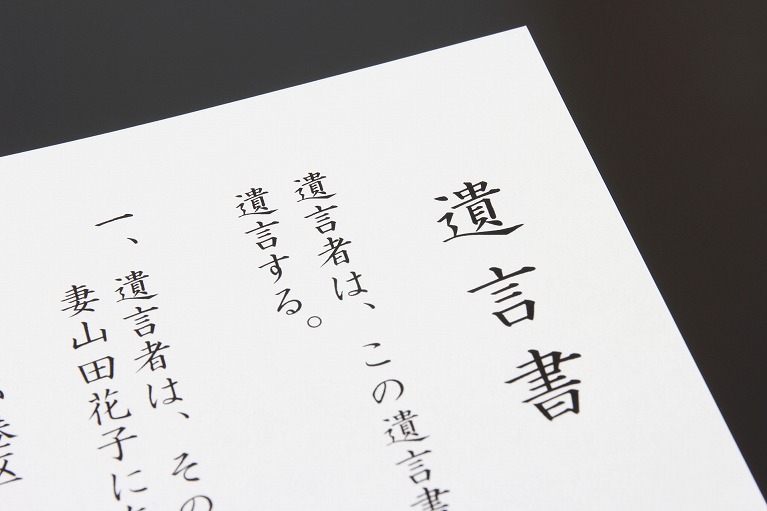 民法は法定相続人の範囲とその相続分(法定相続分)を定めていますが、遺言の記述はそれらに優先します。財産を残した故人の意思を尊重するためです。「全財産を○○に譲る」と記載があると、○○さん以外の、本来相続できるはずの相続人が一切相続できないというケースも起こり得ますが、こうした遺言も決して無効ではありません。
民法は法定相続人の範囲とその相続分(法定相続分)を定めていますが、遺言の記述はそれらに優先します。財産を残した故人の意思を尊重するためです。「全財産を○○に譲る」と記載があると、○○さん以外の、本来相続できるはずの相続人が一切相続できないというケースも起こり得ますが、こうした遺言も決して無効ではありません。
しかし、民法では一定の範囲の法定相続人に限って、最低限の財産の相続を確保できる権利を保障しています。それを遺留分といいます。
遺留分が認められる相続人の範囲と割合は以下の通りです。
- 遺留分権利者は法定相続人である、配偶者、直系卑属(子、子の代襲相続人)、直系尊属(親)のみ
- 遺留分の割合は配偶者、直系卑属は全財産の2分の1、直系尊属は全財産の3分の1
権利者は直系に限られ、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められません。
遺留分は自動的に相続できるものではありません。遺留分権利者は相続が開始され減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。1年を過ぎると時効によって遺留分を請求する権利は消滅します。
遺留分を請求(遺留分減殺請求)するには
遺留分減殺請求をするには、贈与や遺贈を受けた相手方に意思表示をし、その後交渉に入ります。以下のような流れになります。
- 内容証明郵便等によって相手方に意思表示します。
- 相手方と協議を行って遺留分を返還してもらうよう交渉します。
- 応じてもらえない場合、家庭裁判所での調停又は訴訟を起します。
1.の段階で内容証明郵便等によって遺留分減殺請求を行う意思があることを伝える必要があります。遺言執行者がいる場合には、遺留分減殺請求権を行使することを知らせておきます。
遺留分についてよくある質問
遺留分を減殺請求した方
遺留分を減殺請求したましたが相手方から何の反応もありません。どう対応したらいいでしょう?
あなたからの意思表示を受け、相手方は減殺の範囲内で財産を返還しなくてはなりません。ただ、相手方が遺留分を認識していない場合、遺留分額に認識の違いがあるような場合、感情的なもつれがあるような場合には、積極的に返還に応じてもらえないケースもあります。相手方と返還についての交渉を行う必要があります。それでも合意形成ができない場合には、家庭裁判所での調停、地方裁判所への提訴などを行います。
遺留分減殺請求で共有することになった不動産の扱いについて、どうしたらいいでしょう?
不動産以外におもな相続財産がない場合には遺留分に当たる不動産を共有することになります。共有名義とすることが目的であれば所有権の一部の移転登記手続を行います。
共有状態を解消したいのであれば共有物の分割を求め、分割方法について協議をすることになります。以下のような方法が考えられます。
- 不動産を現物分割する(持ち分に応じて不動産を分割し、それぞれ登記する)
- 共同で売却し、その代金を持ち分割合に応じて配分する
- 持ち分を相手方に買い取ってもらう
協議がまとまらない場合には、共有物分割請求訴訟を検討します。
遺留分について現金でもらうことは可能でしょうか?
必ず現金でもらえるとは限りません。
民法の1041条1項には「受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる」と書かれています。これを価額弁償といいます。相手方がこれに応じてくれる場合には、現金で受け取ることができます。ただ、価額弁償を遺留分権利者側から選択することはできません。したがって、相手方が価額弁償に応じない場合には、権利分を現金で受け取ることはできません。なお、個別時案によって異なる場合がありますので、ご相談ください。
遺留分減殺請求に対して金銭以外の財産を渡すといわれました。応じなければなりませんか?
応じる義務はありません。
遺留分減殺請求には相当分を現金で支払う価額弁償という形がありますが、双方の合意なしに現金以外の財産で行うことはできません。なお、個別時案によって異なる場合がありますので、ご相談ください。
遺留分減殺請求を受けた方
遺留分減殺請求を受けました。どう対応したらいいですか?
遺留分権利者と財産の返還について協議することになります。交渉を求められた段階でこれに応じればいいでしょう。ただし、遺留分減殺請求を受けて財産が共有状態になった場合、収益物件が含まれていたり、価額弁償予定の財産の価値が上がっていたりするような場合には、積極的に協議を行って早期の解決を図ったほうが有利なケースもあります。
遺留分を現金で請求されています。応じる必要がありますか?
財産返還に代わって現金で支払う価額弁償は、遺産を相続した方が自らの判断で行うことができます。ただ遺留分権利者に認められた選択ではありませんので、必ずしも現金で支払う必要はありません。また、相手が合意しない場合、必ず価格弁償が認められるというものでもありません。
遺留分として特定財産の指定がありますが、応じる必要がありますか?
要求に応じる義務はありません。たとえば、遺留分権利者から遺産を相続した方が住んでいる自宅を要求されるようなケースです。遺留分権利者の共有持ち分の登記に応じるか(共有名義)、持ち分相当の金銭を支払うなどの方法を探ることになります。
遺留分に関して弁護士に依頼するメリット
 遺言によって贈与や遺贈を受けた方も遺留分権利者も、そもそも遺留分についての知識がない、専門知識がないために対抗策を立てられない、といったことはよくあります。贈与や遺贈を受けた方にとっては、請求されれば対応せざるを得ませんし、遺留分権利者にとっては、遺留分減殺請求の意思表示が必要で、また、請求しないでいると時効で権利が消滅してしまいます。
遺言によって贈与や遺贈を受けた方も遺留分権利者も、そもそも遺留分についての知識がない、専門知識がないために対抗策を立てられない、といったことはよくあります。贈与や遺贈を受けた方にとっては、請求されれば対応せざるを得ませんし、遺留分権利者にとっては、遺留分減殺請求の意思表示が必要で、また、請求しないでいると時効で権利が消滅してしまいます。
基本的には双方の協議で合意を目指すものですが、簡単には解決しないことのほうが多いようです。
遺留分減殺請求に関して弁護士に依頼することは次のようなメリットがあります。
解決への見通しが立つ
弁護士が事情を把握し、遺贈分という権利について双方へ法律に基づいて確かな情報をお伝えし、解決への道筋を提案します。
相手方と話す必要がない
弁護士は代理人としてすべての交渉を引き受けます。したがって、相手方と話をする苦痛や不安から解放されます。相手方から直接連絡があった際には「すべて弁護士に話してください」といっていただいて結構です。
法的手段で解決に結びつけられる
遺留分の権利を知らない相手や、遺言はすべてに優先すると思い込んでいる相手だった場合、法律に則って相手方に説明をし、協議のプロセスへ導きます。万一、協議で解決しない場合の調停、訴訟という過程でも、手続や出廷などすべて弁護士が代理を務めます。
書面の準備など繁雑な作業を任せられる
調停や訴訟には多くの書面を用意する必要があります。専門家である弁護士がこれらの負担を引き受けますので、繁雑な作業をする必要はありません。
専門家がサポートしてくれる安心感がある
遺留分減殺請求は正当な権利の行使である一方、遺言に異を唱える手続でもあるため、精神的な苦痛やストレスを抱えてしまうこともあるでしょう。弁護士が担当することで精神的にもサポートを受けることができます。
特別受益について
特別受益とは
相続人が被相続人から特別に受けた利益のことを特別受益といいます。
よくあるケースが、
- 住宅取得費用を出してもらっていた
- 新居の土地の贈与を受けていた
- 大学進学費用の援助を受けていた
などで、これらは特別受益に当たります。
特別受益があったと認められた場合、特別受益分を遺産に足して、その総額(全遺産+特別受益分)を相続人で分割します。
特別受益の対象
特別受益は遺贈、死因贈与、生前贈与が対象となります。
遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。これは被相続人が単独で(財産を贈る相続人に知らせずに)行うことができます。
死因贈与
死因贈与とは、被相続人が亡くなったときに特定の相続人に財産が与えられる贈与契約です。被相続人の生前に双方で合意をしておく必要があります。
生前贈与
生前贈与とは、被相続人の生前に贈与契約によって財産を贈与することです。生前贈与で特別受益が認められるのは、以下のようなケースです。
結婚や養子縁組のための贈与
- 結婚の際の持参金。嫁入り道具、支度金
- 養子縁組の際の居住用の家
生計の資本としての贈与
- 住居新築時の費用援助
- 新居用の不動産・土地の贈与
- 大学進学や留学のための学資援助
特別受益の注意点
生前や死後に贈与された経済的利益はすべて特別受益になるかといえば、そうではありません。以下のようなケースでは特別受益は認められません。
少額の贈与
贈与があったとしても小さな額であれば特別受益とは評価されません。
相続人以外への贈与
特別受益は相続人に限って認められます。相続人ではない第三者が受益を受けていたとしても、特別受益の対象にはなりません。したがって、内縁者、友人知人などへの高額な贈与があった場合には、特別受益の主張をすることはできません。
特別受益は自動的に認められるものではなく、特別受益を受けていない相続人が主張し、協議や調停で解決をする必要があります。
寄与分について
寄与分とは
 寄与分とは、被相続人の財産を増やす、あるいは減るのを防ぐことに協力した人がいるような場合に、その貢献(寄与)分を優遇する制度です。民法の規定によれば、「被相続人の事業に関する労務の提供」または「財産上の給付」、「被相続人の療養看護その他の方法」によって「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」場合に認められるものです。
寄与分とは、被相続人の財産を増やす、あるいは減るのを防ぐことに協力した人がいるような場合に、その貢献(寄与)分を優遇する制度です。民法の規定によれば、「被相続人の事業に関する労務の提供」または「財産上の給付」、「被相続人の療養看護その他の方法」によって「被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした」場合に認められるものです。
たとえば、子である相続人が親である被相続人の事業を手伝って事業を維持・発展させたり、親の生活を扶養してきたり、看護・介護などで医療費の支出を抑えたりしてきたケースなどでは寄与分が主張できます。
しかし、事業の手伝いをしたり、財産上の給付を行ったり、介護などを続けてきたりしたとしても、被相続人の財産が減ってしまったり、とくに増えていなかったりする場合には寄与分は認められないでしょう。
寄与分が認められた場合、相続財産の総額から寄与分相当を差し引き、残りを相続人が法定相続分にしたがって相続します。その上で、控除した寄与分を、寄与が認められた相続人に加算します。
寄与分は法定相続人にのみ認められます。
寄与分の具体例
具体的な例で寄与分が認められた場合の相続例を示して見ましょう。
被相続人Aには配偶者Bと2人の子どもC、Dがいます。相続人はこの3人だけです。Aの遺産は1億6,000万円でした。
通常の法定相続分で分割した場合、
子どもC 1億6,000万円×1/4=4,000万円
子どもD 1億6,000万円×1/4=4,000万円
となります。
ここで、子どもCだけがAの事業を手伝って発展に貢献したことから、寄与分が2,000万円認められたとしましょう。総相続財産から寄与分の2,000万円を控除した金額を3人の相続分にしたがって分けます。配偶者は7,000万円、子どもC、Dは3,500万円ずつとなります。ここで控除分の2,000万円は子どもCに加算されますので、
子どもC (1億6,000万円-2,000万円)×1/4=3,500万円+2,000万円=5,500万円
子どもD (1億6,000万円-2,000万円)×1/4=3,500万円
このような金額で相続することになります。
当所にて遺留分減殺請求を行った事例紹介
ご相談内容
母親が亡くなった後に、遺言書を裁判所にて開封した際に、「家を継ぐ長男にすべての財産を譲る」と記載されていました。「遺言書は法定拘束力をもつ」と聞きましたが、次男である私は何も相続することはできないのでしょうか。
当所のアドバイス
次男である場合、法定相続人となり「遺留分」という「一定の遺産を受ける権利」を有しています。長男に対しその事を伝え、それでも難しい場合は、遺留分減札請求の申し立てをしてみてはいかがでしょうか。
結果
遺留分減殺請求は認められ、法律で定められた遺産額の2分の1に相当する財産を受け取ることができました。
弁護士の視点
遺言書が合ったとしても、法律の枠組みを越えた内容に関しては、手続きして対応することができます。また、今回の遺留分減殺請求ですが、相続開始から1年以内に申立てを行わないといけません。自然発生的に生じる権利ではありませんので注意が必要です。